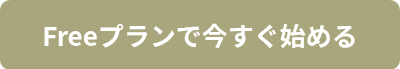新人教育マニュアルの作り方とわかりやすくするコツ7選!
新人教育マニュアル作成のポイントとコツを紹介。Diveを使った効率的な動画マニュアル作成方法をご提案。

目次
-
3-1.ゴールを明確にする
3-2.目的や判断基準を記載する
3-3.現場のリアルを反映する
3-4.テキストだけに頼らない
3-5.専門的な表現はなるべく避ける
3-6.定期的に更新する
3-7.マニュアルへのアクセス方法や問合せ先を明記する - 4.新人教育マニュアル作成にはDiveがおすすめ
4-3. 充実した機能で様々な運用方法に対応できる - 5.まとめ
1.新人教育マニュアルとは

新人教育マニュアルには、以下の4つの基本構成を盛り込むのが効果的です。
・基本的なビジネスマナー
新人教育マニュアルには、まず基本的なビジネスマナーを盛り込むことが重要です。社会人経験のない新入社員にとって、挨拶の仕方、電話対応、メールの書き方、敬語の使い方などは、現場に出る前に身につけておきたい基礎スキルです。
学生時代にある程度のマナー教育を受けている人もいますが、実際のビジネスシーンで求められる振る舞いとの間にギャップがあることも多いため、具体例を交えながら丁寧に説明するとよいでしょう。
・ 企業理念・人事手続き・社内のルールなどの基本情報
企業理念やビジョン、人事に関する手続き、社内の就業規則など、会社の基本情報も新人教育マニュアルに欠かせません。これらは日々の業務に直接関わるわけではありませんが、組織の一員として働くうえで必要な前提知識です。
特に社内特有のルールや文化は、新人にとって見えづらく、質問もしにくい分野のため、マニュアルで体系的にまとめておくと安心感に繋がります。
・ 社内で活用しているツールの利用方法
業務で使用する社内ツールの使い方も、新人にとってはつまずきやすいポイントの一つです。チャットツール、勤怠管理システム、ファイル共有サービスなど、どのような場面でどのツールを使うのか、具体的な操作手順とともに説明しましょう。
また、ツールごとにルール(ファイル名の管理ルール、返信のタイミングなど)がある場合は、併せて記載することで業務ミスの防止にも繋がります。
・ 業務に関するマニュアル
新人が実際に担当する業務については、作業手順やポイントをわかりやすく整理した業務マニュアルを作成しましょう。実際の業務と同じ流れで構成した動画にすることで、どのタイミングで何をすべきかが明確になります。
さらに、図や写真、動画を取り入れて視覚的に理解しやすくすると、実際の現場でもスムーズに行動できるようになります。新人が一人で業務をこなせるようになるための「道しるべ」となる内容を意識しましょう。
アップロード&放置で動画編集9割完了!動画・AR手順書システム「Dive」
3.新人教育マニュアルをわかりやすくするコツ7選
マニュアルに含める基本事項を把握したら、いよいよマニュアルの制作に移ります。本章では、新人教育マニュアルを制作する際の7つのコツについて詳しく確認していきます。
3-1.ゴールを明確にする
新人教育マニュアルを作成するうえで、最初に重要なのは「ゴールを明確にすること」です。新人にどのレベルまで到達してほしいのか、いつまでに何をできるようになってほしいのかを最初に定義しておきましょう。
たとえば、「基本的な業務が一人でできるようになる」「社内のツールを使いこなせるようになる」など、具体的なゴール設定があると、業務の定着、企業文化の理解、自走力の育成などにとても効果的です。
ゴールが曖昧なままだと、マニュアルの内容も散漫になり、教える側も学ぶ側も迷子になりがちです。逆にゴールが明確なら、必要な情報や順序も自然と整理され、マニュアルの構成がスムーズに決まります。
さらに、新人自身も「どこに向かっているのか」がわかるため、安心感を持って学習に取り組むことができます。可能であれば数値や行動で測れる形に設定し、達成基準を明示しておくと、評価もしやすくなります。
3-2.目的や判断基準を記載する
マニュアルには単にTODOを羅列するのでなく、「なぜそれをやる必要があるのか」という目的や「どう判断するべきか」という基準も併せて記載することが大切です。
目的がわからないまま業務をこなしてしまうと、新人は応用力が育たず、言われたことしかできない「指示待ち」状態になりやすいからです。
たとえば、「この手順は一定の品質を維持するために重要である」など、背景となる意図を明示しましょう。
また、イレギュラー対応が必要な場合でも、「この場合は何を優先するか」「どういう基準で判断するか」を記載しておくと、全てを網羅せずとも新人が自ら考えて動けるようになります。
目的や判断基準をセットで伝えることで、新入社員を「指示待ち人間」にしてしまわないためにも、自分で行動できるための指針を示すことが重要です。
3-3.現場のリアルを反映する
マニュアルは理想論でなく、実際に現場で起こっているリアルな情報を反映することで、より実用的で役立つマニュアルになります。机上の理論だけでは、新人が現場に出たときに「話が違う」と戸惑ってしまう原因になります。
現場特有の事情や、よくあるミスや、つまずきやすいポイントもなど、現場にいる人でなければわからない「リアルな情報」を合わせて紹介しておくと、新人が注意深く業務にあたることができます。
現場社員の声を聞きながら課題や実例を盛り込みマニュアルを作成することで、実践に即した、より使えるマニュアルになります。
新人にとっても「現場の空気感」をあらかじめ理解できるため、不安が和らぎ、スムーズな立ち上がりにつながります。
3-4.テキストだけに頼らない
新人教育マニュアルをよりわかりやすくするためには、テキスト情報だけに頼らず、図解や写真、動画など視覚的な表現を積極的に取り入れることが効果的です。
特に操作手順や機械作業、ツールの使い方など、動きがあるものは文章だけでは伝わりづらいことが多いため、実際の画面や作業風景を見せたほうが理解が深まります。
最近では動画マニュアル作成ツールも充実しており、スマートフォンで簡単に動画を撮影・共有できる環境も整っています。図やチャートを使ってフローを可視化するだけで、新人が自分のペースで繰り返し学習できる環境をつくることができます。
できるだけ多様な表現方法を取り入れて、「読むだけ」のマニュアルから「見てわかる」マニュアルを目指すと効果的です。
3-5.専門的な表現はなるべく避ける
新人教育マニュアルは、できるだけ専門用語や難解な表現を避け、誰にでもわかる平易な言葉で書くことが大切です。
特に新卒社員や異業種からの転職者は、業界用語や社内独自の言葉に馴染みがなく、無意識に使われる専門的な表現に戸惑いやストレスを感じがちです。
もしどうしても専門用語を使う必要がある場合には、必ず簡単な解説を添えるようにしましょう。
また「略語」は社内では当たり前でも、新人には意味がわからないものが多く、混乱の原因になります。
基礎的な知識すら不安な状態で「暗黙の了解」や「略語」が多用されていると誤解を生みやすいため、誰が読んでも理解できるマニュアルを作成するために、言葉選びには十分に配慮が必要です。
新人教育マニュアルは、ベテラン向けではなく、あくまで「何も知らない人」が対象であることを常に意識して作成することが重要です。作成したマニュアルは、経験の浅い社員に確認してもらうとより安心です。
3-6.定期的に更新する
新人教育マニュアルは、一度作成したら終わりではなく、業務内容、使用ツール、社内ルールなどの変化に合わせて定期的な更新が必要です。
古い情報がそのまま残っていると、新人に誤った知識を与えてしまい、混乱やミスの原因になるため、最低でも年に一度はマニュアルの内容を総点検し、改訂を行う体制が不可欠です。
また、実際にマニュアルを使った新人や指導者からフィードバックをもらい、現場の変化や使い勝手に応じてブラッシュアップしていくことも大切です。
更新担当者や更新スケジュールをあらかじめ決めておくと、メンテナンスが滞らず、信頼されるマニュアルとして機能します。
常に「今の現場に合った、最新の情報を伝える」意識を持ち続けることが、マニュアルを生きたツールにするポイントです。
3-7.マニュアルへのアクセス方法や問合せ先を明記する
どんなに素晴らしいマニュアルを作成しても、必要なときにアクセスできなければ意味がありません。そのため、マニュアルの保管場所や閲覧方法を明確にしておくことは非常に重要です。
オンラインストレージや社内ポータルサイトなど、どこに保存されているか、新人がすぐにわかるようにマニュアルを運用しましょう。
また、マニュアルの内容だけでは解決できない疑問が出てきた場合に備えて、問い合わせ先(担当者名・連絡方法など)を必ず記載しておくと、誰に何を聞けばいいかが明確になっているので、新人の不安が軽減され、スムーズな対応が可能になります。
「困ったらここにアクセス」「わからなければこの人に聞く」という安心感を持たせることで、新人の不安が軽減され、スムーズな解決が可能になります。
アップロード&放置で動画編集9割完了!動画・AR手順書システム「Dive」
4.新人教育マニュアル作成にはDiveがおすすめ
新人教育マニュアルには主に紙媒体とデジタル形式の二種類がありますが、管理のしやすさや確認の手間を考慮すると、デジタル運用がおすすめです。
特に、クラウド上で運用できるマニュアルであれば、社内での共有が円滑に行えるだけでなく、テレワーク時にも新人が自主的に学習・復習に取り組みやすくなります。
弊社の「Dive」のような、クラウドベースで活用できる動画マニュアル作成ツールには、次のような特長があります。
4-1.AIによる動画分割と簡単編集で使えるマニュアルが完成する
動画マニュアル「Dive」では、AI技術を活用して、誰でも簡単に高品質な動画マニュアルを作成できる機能が備わっています。
作業動画があればAIが動画内の解説内容、作業者の動きをもとに手順分割を自動で行うため、長い動画データを手作業でカットする必要がありません。
他社にはない”動きだけでも手順分割ができる”現場利用に特化したユニークなAIを搭載しているため、音声がなくても動画内に映る作業者の動きを分析して動画分割を実行できます。これにより、編集の負担が大きく軽減され、作成作業がスピーディに進みます。
また、動画内で解説されている内容は文字起こしされ、各手順を要約したタイトルを自動生成する機能も搭載されています。
雑音が多い環境でも正確に音声を識別して補完したり、小さな声や話し方のクセがある聞き取りづらい部分の認識にも強いAIを活用しています。一般的な文字起こしAIよりも日本語の認識精度が高いのも特徴の一つです。
さらに、説明文はあらかじめ用意された入力フォーマットに沿って簡単に追加できるため、文章作成に慣れていない担当者でも安心してマニュアルを作成することができます。
オブジェクト(矢印や枠などのマーク)や、補足説明用の画像を挿入できる機能も備わっており、視覚的にわかりやすいマニュアル作成が可能です。
こうした多機能ながら直感的に使える設計により、専門的なスキルがない人でも、高品質なマニュアルを短時間で完成させることができるのがDiveの大きな魅力です。新人教育マニュアル作成においても、スピードと質を両立できる頼れるツールです。
4-2.作業の手順毎に動画・文章を表示して繰り返し再生できる
Diveの特徴のひとつは、作業の手順ごとに動画が繰り返し再生される点です。これにより、新人は一連の業務フローを自分のペースで確認しながら学習することが可能になります。
動画では実際の動作や手順が映され、すぐ横に文章で手順やポイントの解説があるため、「読む・見る・実践する」という学習サイクルが自然に回せる設計になっています。
また、手順ごとに再生が区切られているため、わからない部分だけをピンポイントで見返すことができ、効率的な復習ができます。
現場においても、スマホやタブレットを片手に作業を進めながら動画を確認できるため、理解と行動を一致させながら作業習得が進みます。実際の作業中に確認しながら学ぶことで、座学だけでは身につかない「実践力」を早い段階で養うことが期待できます。
さらに、Diveには手順ごとにタスク(チェック項目)を設けることができ、動画視聴後に簡単な問題形式で理解度を確認する機能もあります。
このチェック機能により、「ただ見るだけ」では終わらず、知識の定着を図ることができます。こうした仕組みが、単なる閲覧型マニュアルではない、実践的な教育ツールとしてのDiveの強みです。
4-3.充実した機能で様々な運用方法に対応できる
Diveは、マニュアル作成と運用の両面で多彩な機能を備えており、さまざまなニーズに柔軟に対応できる点が大きな強みです。
必要な情報をすぐに探し出せる「検索機能」が搭載されているため、大量のマニュアルデータの中から目的のコンテンツに素早くアクセスすることができます。業務が多岐にわたる現場では、スピーディな観覧に欠かせない重要な機能となります。
また「フォルダ管理機能」により、部署別や業務別など、整理された形でマニュアルを保存・分類できるため、社内の情報管理もスマートに行えます。
フォルダごとに閲覧権限を設定できるため、各ユーザーに「本当に必要な情報だけ」を届けることができます。新人向け、管理職向け、専門部署向けなど、ターゲットに合わせたマニュアル提供が可能になり、情報過多による混乱を防ぐことができます。
さらに、Diveは作成したマニュアルをソフトやアプリで再生・観覧するだけでなく、mp4やPDF、Excelファイルとしても出力できるため、用途に応じた多様な活用が可能です。
たとえば、研修資料として配布する際にPDF化したり、管理用リスト作成時にExcel出力するなど、状況に合わせた柔軟な対応ができます。
加えて「共有機能」による関係者全体へのスムーズな情報展開もできるので、テレワーク環境下での研修でも問題なく運用することができます。
学習に使われたマニュアルは「利用状況の確認機能」により指導者や管理者が「誰がどのマニュアルをどれだけ閲覧したか」や「的確にタスク(チェック項目)を回答できているか」などを確認できるため、新人の学習進捗管理にも活用できます。
このように、Diveは作るだけでなく、使いやすく、管理しやすく、効果測定まで可能な“運用を見据えた”マニュアル作成ツールになっています。
アップロード&放置で動画編集9割完了!動画・AR手順書システム「Dive」
5.まとめ
新人教育マニュアルは、単なる業務の手順書ではなく、会社の文化や価値観を伝える道しるべとも言えます。マニュアルの質が高ければ高いほど、新人は安心して業務に取り組むことができ、早期に戦力化されやすくなります。
今回は、マニュアルに盛り込むべき内容を解説し、わかりやすくいマニュアルを作成する7つのコツを紹介しました。特に、現場の声を反映し、視覚的な表現を取り入れたマニュアルは、新人にとってもわかりやすく、定着率を高める重要な要素です。
当社の動画・ARマニュアルツール「Dive」ではより簡単で、直感的に動画マニュアルの制作・運用ができる機能をご用意しております。
視覚効果の高いマニュアルにより効果的に学びを支援することで、口頭ではなかなか伝えるのが難しかった業務の「見るだけで理解できる」を実現し、新人教育の質とスピードを向上させます。
さらに詳しい情報は、以下より資料ダウンロードが可能です。
ご覧いただきありがとうございました。
Diveでは手軽に試せる「Freeプラン」をご用意しております!
”1日1動画から始められる”この機会に、操作感やAI機能の実用性を体験していただけると幸いです。
▼▼▼”動画マニュアル導入の第一歩”としてご活用ください▼▼▼