教育の見える化で人材育成を効率化!現場教育が“曖昧”になる根本原因とその打開策とは!?
新入社員やアルバイトスタッフなどの現場教育にお困りの方必見! マニュアルの利用履歴が教育の効率化を強力サポート!
OJTの教育効果が実感できない管理職クラスの方必見!動画マニュアル×スキルマップで教育改革を実現!Diveの”スキルマップ機能”をご紹介!
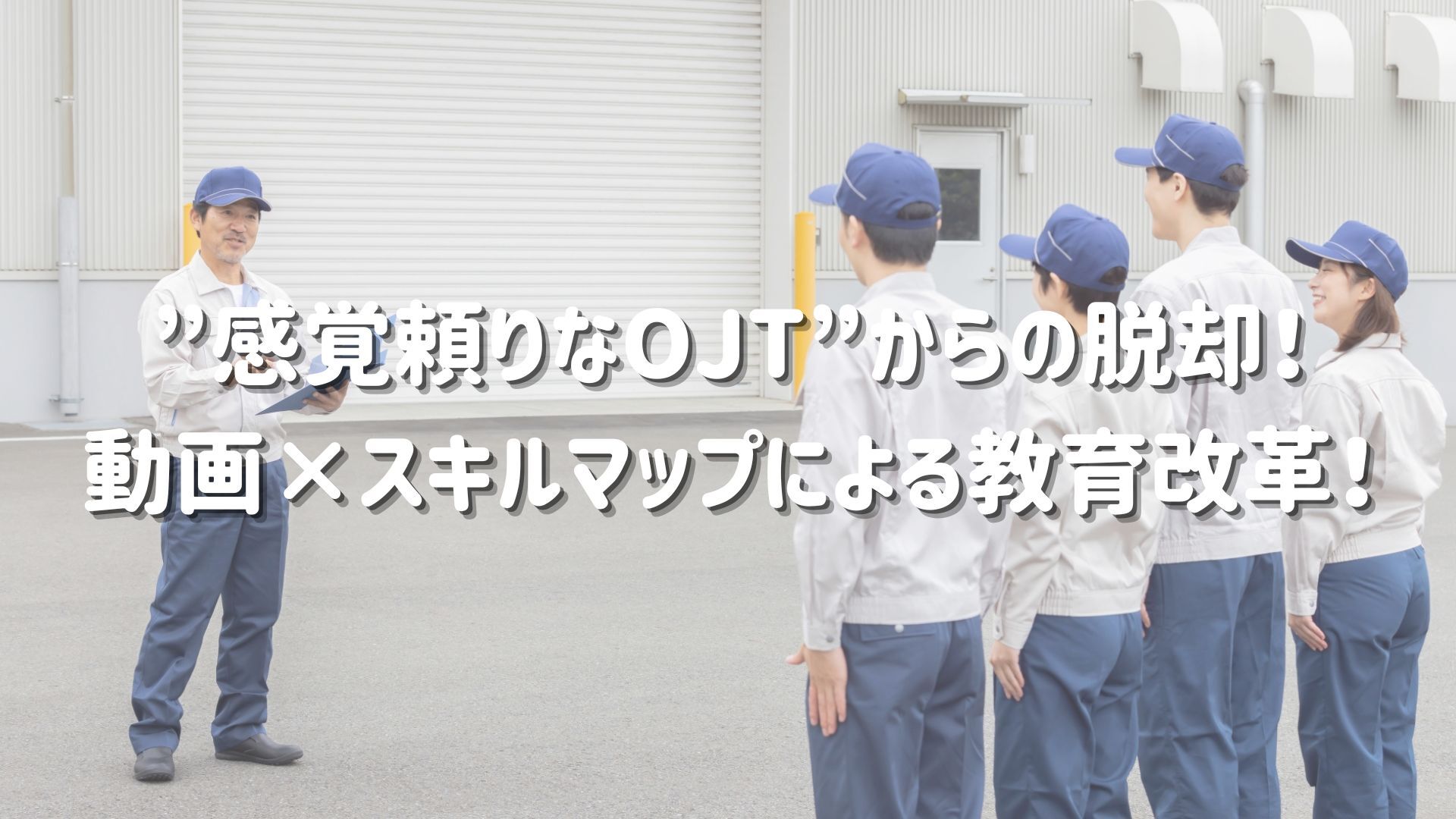
新入社員やアルバイトスタッフなどの現場教育にお困りの方必見! マニュアルの利用履歴が教育の効率化を強力サポート!
オフライン環境でも活用できる動画マニュアルを検討している方必見! 必要な時にいつでも確認できるマニュアル運用で万全な安全教育を実現! Diveの”オフライン動作・MP4出力機能”のご紹介!
現場DXの取り組みとしてスマートグラスの活用を検討している方必見! 現場作業員に手順書が使われないを解決する新常識! 動画マニュアルのハンズフリー観覧が実現す次世代の現場教育!