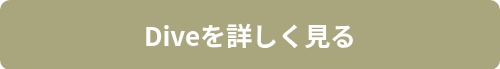動画マニュアルを作成するべき業務64選!
動画マニュアルの作成を始めようとしている方必見!
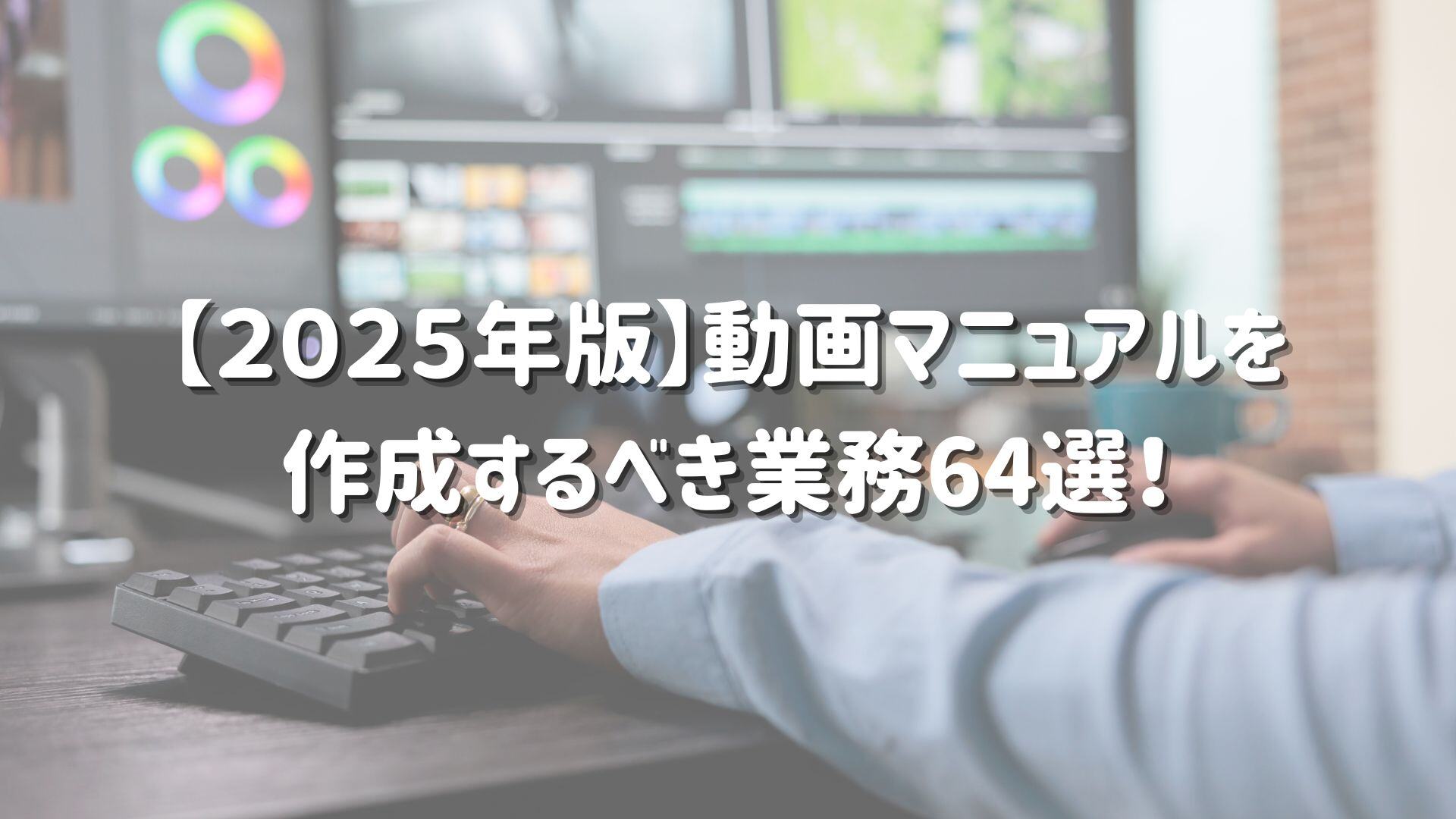
目次
-
3-1.操作・作業系業務
3-2.システム・ITツール運用系業務
3-3.安全・緊急対応系業務
3-4.接客・コミュニケーション系業務
- 4.まとめ
主に、動画マニュアルには以下のような利点があります。
・視覚と聴覚でより直感的に理解を深められる
・現場のリアルな動きをリアルに再現できる
・時間や場所に囚われずに手軽に参照できる
・指導者によるバラつきをなくして教育を標準化できる
・短い時間で効率的に業務を習得できる
近年、多くの企業が業務マニュアルを動画化しており、その背景にはテキストだけでは伝わりづらい業務の流れや現場のリアルな動きを、より直感的に伝える必要性が高まっているという要因や、人手不足により人材教育が困難になりつつある現場で、効率的な標準化が求められているという要因があります。
2.動画マニュアルにするべき業務の特徴
動画マニュアルが特に効果を発揮する業務の一つは、人の手作業や機器の操作・点検、対人コミュニケーションなど”実際の動きややりとりの流れ”が重要な業務です。
また、ITシステムの使い方や、安全対策など文字や画像だけでは習得しづらく、日常業務より頻度が少ないため”動画で見せる方がわかりやすく効率的”になるような業務に有効です。
反対に、就業規則などのルールや制度説明は、視覚的な情報が少なくて済む傾向にあるため、テキストマニュアルの方が向いているケースもあります。
したがって、動画マニュアルを作成するべき業務は以下の4つに分類することができます。
・操作・作業系業務
・システム・ITツール運用系業務
・安全・緊急対応系業務
・接客・コミュニケーション系業務
では、具体的に4つの分類の中にはどのような業務があるのか、次章で見ていきましょう。
3.動画マニュアルにするべき業務64選!
3-1.操作・作業系業務
電子機器工場や化学工場、食品工場、物流倉庫などで、実際に「手を動かすこと」が中心の業務では、作業の順序や動作の正確さが求められます。
また、製造業・物流業に限らず、レストランやスーパーマーケットなどのサービス業でも「機械の操作」や「手作業での業務」は多くあるため、文章だけでは伝わりにくい“動きのニュアンス”を伝えるために、動画での視覚的な説明が非常に効果的です。標準化や品質保持、習熟時間の短縮にも貢献します。
・機械装置の操作
ボタン操作や作業手順などは、実際の動作を見ながら学ぶことで誤操作を防ぐ役割があり、テキストベースのマニュアルでは伝わらないニュアンスも把握できるため、作業の習得も早くなります。
・組み立て作業
組み立て順や部品の向き、手の動きが重要な作業を動画によって直感的に理解しやすくすることで、間違いを減らせます。
・ラベルの貼り付け作業
位置、角度、貼り方など製品の均一化を目的としたマニュアルや、指先の使い方などの感覚的な部分も動画で見せることで、品質のばらつきを減らせます。
・工具の使い方
工具の正しい持ち方や使用時の注意点をあらかじめ明記して、安全な方法を実演で示すことで事故の予防につながります。
・フォークリフトの操作
荷物の積み下ろし方や走行ルールなど、安全性と効率の両方を確保するために、現場での操作や、厳密なルールを動画化することで効果的に学習することができます。
・検品・検査作業
合格・不合格の基準、チェック項目の視点などを動画で示すと、品質基準の理解が統一され、ミスが減ります。傷・汚れ・異物の見つけ方など、視点の動かし方も含めて動画で習得することでさらに精度が上がります。
・ライン作業
作業スピードのリズムや荷物の扱い方を映像で示すことで、現場でのリズム感や段取りが自然に身につきます。また、緊急停止ボタンの位置や押し方など、万が一の時に備える知識も動画での反復学習が効果的です。
・部品の仕分け
多品種・少量の仕分けなどでは、識別方法や置き場所のルールなどを動画で明確に共有することで作業のミスを減らすことができます。
・溶接作業
溶接棒の選定方法や、溶接時の手の動かし方、防塵マスクなどの保護具を使った安全の確保など、一連の作業を動画マニュアル化することで、事故防止とスキルの安定が期待できます。
・塗装作業
下地処理や実際の塗装作業など仕上がり具合を左右する工程で文章では伝わりにくい部分を、動画で見せることで、作業品質を合わせるのに有効です。
・ねじ締め作業
トルクや軸力、ねじ締めの順番、部品の材質、潤滑状態の影響などを適切に管理するために、正しい数値や“加減”を動画で表現することで、標準化が期待できます。
・バリ取り作業
バリの出やすい箇所や、出やすいバリの形状、バリの取れやすい方向などを動画で見ることで、ヤスリなどの工具の使い方や、力加減などを直感的に学ぶことができます。
・資材の入出庫・棚卸し作業
バーコード確認や数量チェック、積み荷の順番、取り違え防止対策などを動画で示すことで、作業効率と正確性の両立が図れます。
・梱包作業
包装材の選び方や梱包の丁寧さなど、作業の完成形を動画で示すことで品質を均一化しやすくなり、新人でもすぐに基準を理解できます。
・ピッキング作業
商品の配置や棚番号の読み方など、現場の流れを視覚的に覚えられるため、新人でもすぐに広い倉庫内で効率よく動けるようになります。
・通い箱やトレーの扱い方
通い箱やトレーの積み方や持ち方、並べ方など細かな注意点を動画で説明することで、破損や怪我のリスクを抑えられます。
・清掃作業
使用道具の持ち方や洗浄手順、清掃順序などを可視化することで、ムラのない清掃が可能になります。衛生管理の強化にも有効です。
・商品陳列
商品陳列の美しさや並べ方のルール、効率のよい品出しルートなどを動画で示すことで、売り場の統一感が出て、売上にもつながりやすくなります。
・レジ締め作業
金額確認や帳票処理など正確性が求められるレジ締め作業は、動画で正しい流れを確認できると安心して作業に取り組むことができます。
・食事の盛り付け
盛り付けの見た目やバランスは文章では伝わりづらいため、手順や完成品を動画で見せることで料理の品質が安定します。
作業者の動きを元に自動で手順分割!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」
3-2.システム・ITツール運用系業務
ソフトウェアやクラウドツールなど、画面操作を伴う業務は「すぐに確認できる」ように仕組化することで「何度も同じことを教える」などのムダな時間を減らす効果が期待できます。
複数の操作手順や設定項目がある業務では、静止画よりも画面録画形式の動画がとくに有効で、実際に「同じ画面で操作する」ことで入力漏れや操作ミスを防ぐことができます。マニュアル化することで、習得の個人差を減らし、誰でも同じ品質で作業できることが特徴です。
・CADなどの専門性が高いソフトの社内独自運用
CADなどの設計ソフトにおいて、メーカーから提供されている操作マニュアルとは別に、会社・部署で独自運用している使い方などがあると思います。その際に、テキストベースだと人によって解釈が異なったり、作成自体に時間を要するため、一連の様子を動画で残すことで上記課題を解決できます。
・勤怠管理システムの操作
勤怠管理システムは打刻や有休申請、修正申請など操作項目が多いため、新人研修の一環として動画マニュアル化して、具体的な画面操作を示すことでミス防止と定着が図れます。
・社内ポータルの操作
多機能で階層も深い社内ポータルは、操作手順を動画で可視化することで、迷わず目的の情報やデータにアクセスできます。
・メールの基本運用
件名・本文・署名・CC/BCCの使い方など、ミスが許されない社内外メールをテキスト+動画でマニュアル化することで全社員のメールリテラシーが均一になります。
・経費精算システムの操作
項目選択や必要な添付書類のアップロードなど人によってばらつきやすい工程が多いため、動画で一連の流れを見せることで正確性が上がります。
・社内チャットの運用方法
チャンネルの使い分けやメンションの活用、社内独自のルールなど、習熟度による差を減らすために動画で基本操作を確認できるようにすることで、徹底した情報共有を定着することができます。
・オンライン会議ツールの操作
会議のスケジュールの設定や画面共有、会議リンクの共有、繰り返し設定などの機能を動画で説明することで、設定ミスやダブルブッキングを防止できます。
・Webブラウザ拡張機能の使い方
拡張機能のインストールや活用例、設定方法などを動画化することで、新しく取り入れる業務効率化ツールに対する心理的ハードルが下がり定着しやすくなります。
・社内資料の共有方法
誤った設定が情報漏洩につながる可能性もあるため、共有範囲や権限の設定を行う手順を動画化して正しく伝えることでリスクを減らす効果があります。
・ファイル名の管理ルール
実際の画面で保存時の操作例や注意点を動画化して、全社員が同じルールで管理することで、検索性が圧倒的に向上します。
・SFA・CRMなどの操作
顧客データの入力・検索・更新の手順を動画で共有すれば、登録ミスや機能の使い忘れ、担当者による情報のバラつきが減らせます。
・タスク管理ツールの運用
タスク作成や進捗チェック、コメント機能などの一連の流れを動画で見せることで、チーム内の運用ルールが統一、定着します。
・アカウント登録・初期設定
初回ログインからセキュリティ設定、プロフィール登録までを動画化することで、画面の動きや手順を視覚的にわかりやすく伝えられ、ユーザーが迷わず操作できます。
サポート工数の削減や顧客満足度の向上にもつながるため、導入初期のサポートに非常に有効です。
・アップデート手順
アップデート手順は一時的かつ不定期な作業ですが、テキストでは見落としやすく操作を誤ると業務に支障が出る作業です。動画マニュアルにすることで、実際の画面操作を見ながら手順を正確に理解でき、スムーズな移行を促進できる点で有効です。
解説内容を元に自動で手順分割!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」
3-3.安全・緊急対応系業務
安全・緊急対応系業務は、主に「頻度は低いが重要度の高い」事故や災害などが起きた時に「迅速かつ正確に行動できるか」を求められる業務が多いです。
テキストでは理解しにくい現場対応の流れや判断基準を、動画で疑似体験的に学ぶことで定着させやすくなり、社員全体への安全意識の浸透や訓練の代替手段として有効です。
・火災時の避難誘導
実際の避難経路や行動をいくつかのパターンに分けて動画で体験することで、緊急時に焦らず行動できるようになり、避難の精度が格段に高まります。
・地震・災害時の初動対応
頭部の保護や安全な場所への移動など、一連の流れを動画で繰り返し学習することで、反射的に行動できるようになります。気象災害時の初動や対応手順を動画で示すことで、冷静な判断と行動がしやすくなります。
・応急処置
ケガややけど、意識不明などの初期対応を動画で事前に学習することで、落ち着いて安全に応急処置ができるようになります。
・AEDの使用手順
AEDの設置場所確認から使用時の音声指示対応までを動画で体感的に学ぶことで、緊急時にも迅速な対応が可能になります。
・消火器の使い方
ピンの抜き方やホースの向け方、噴射時間の目安などを動画で実演することで、いざという時に慌てず消火器を使用することができます。
・非常用放送・館内アナウンスの操作
非常用放送や館内アナウンスの操作は、緊急時に正確かつ迅速な対応が求められるため、事前の理解と習熟が重要です。動画マニュアルなら、実際の機器の操作手順や注意点を繰り返し視覚的に学べ、現場でのイメージがつきやすくなり、非常時にも落ち着いて対応できる力を養えます。
・防犯対策
不審者発見時の通報、声かけ、身の安全の確保など、実例を動画マニュアルにすることで、不審者対応や監視カメラ操作などの流れを視覚的に理解でき、防犯意識と対応力の向上に効果的です。
・感染症対策
手洗い、マスク、消毒の正しい方法や行動制限のルールを動画で伝えることで、全社員に共通理解を持たせやすくなります。
・熱中症対策
室温管理・水分補給・症状チェックなどを動画で分かりやすく伝えることで、職場全体の安全意識向上につながります。
・運転前後の点検
タイヤやライト、ミラーなどの日常点検のやり方を動画マニュアルにすることで、確認すべき箇所や正しい点検手順を視覚的に把握でき、点検の質と意識の向上に役立ちます。
・車両誘導・通行のルール
駐車場や搬入口での車両誘導の手順や合図を動画で統一すれば、事故防止とスムーズな案内が可能になります。また、一方通行や一時停止のルールなど、構内特有の通行ルールを動画で見せることでルールの徹底がしやすくなります。
・工場内の安全確認
作業前後の安全確認項目や注意エリアの把握を動画マニュアルで共有にすることで、点検箇所や正しい確認方法を実際の現場映像で伝えられ、安全意識の向上と確認作業の標準化に効果的です。
・夜間勤務時の安全確認
夜間勤務時は人手が少なく、周囲の状況も見えにくいため、巡回方法や鍵管理、休憩中の対応など、昼間と異なる安全ポイントを動画で解説することで、夜間特有のリスクに対する備えが強化され、安心して勤務できるようになります。
・作業開始・中断時の手順
現場での安全確認や人員把握を確実に行うための点呼方法を動画で共有すれば、作業前の安全体制が整います。また、中断の手順を間違うと事故や故障の原因になるため、スイッチの切り方や再開時の確認手順を動画で示すとより効果的です。
・工具・道具の点検
点検箇所やチェックリストの使い方を動画で説明すれば、使用前後の不備確認が習慣化されて、未然に事故を防いだり、歩留まり向上に繋がります。
・落下物防止対策
棚や高所の荷物管理、落下する可能性がある機器の固定方法などを動画で示すことで、事故を未然に防ぐ意識と方法が身につきます。
・高所作業時の安全対策
高所作業は転落などの重大事故につながるリスクが高く、安全対策の徹底が不可欠な業務です。ヘルメットや安全帯の装着方法、点検手順を動画で学ぶことで、安全帯の正しい装着方法や作業前の確認事項などへの理解が深まり、現場での安全意識と対応力の向上に繋がります。
・騒音環境での安全対策
騒音環境では指示が聞こえにくく事故のリスクが高まるため、事前の安全対策が重要です。
防音保護具の装着手順や、ジェスチャーでの合図方法などを動画マニュアルで共有することで、実際の現場に近い状況を再現できるため、騒音下でも確実に行動できる実践力が養えます。
・セキュリティゲートの使い方
入退室のルールやトラブル時の対応を動画で示すことで、ミスによる警報作動や混乱を防ぐことができます。特に初めて利用する来訪者や新入社員にもわかりやすくすることで、混雑やトラブルの防止につながります。
解説内容&人の動きを元に自動で手順分割!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」
3-4.接客・コミュニケーション系業務
接客・コミュニケーション系業務では、顧客や社内の人とのやりとりを含む業務で、言葉遣い・声のトーン・表情・所作など雰囲気を含めて伝えることが重要です。
模範的な対応を動画で再現することで、ロールプレイや実演による学習が可能になり、サービスレベルの均一化や新人教育をより短い期間で行うことができます。
・接客の基本マナー
挨拶、笑顔、姿勢などは実際の動作を見て真似ることで自然に身につきやすく、NG例と正し例を合わせて動画にすることで学習効果が高くなります。
・受付対応
初めて来た人への声がけ、受付簿の案内、バッジの渡し方など、丁寧な印象づくりが求められる業務は、ロールプレイ動画で実演することで接客品質を統一しやすくなります。
・名刺交換
名刺の渡し方やタイミング、相手との距離感など細かな動作を映像で見せると、交換相手に失礼のない対応ができます。
・クレーム対応
トーンや表情、言葉の選び方などパターンに分けて複数のケースをロールプレイで見せることで、より実践的な対応力が身につきます。
・電話対応
言い回しや受け答えの流れを実演で見せると、スムーズな対応を習得しやすくなります。また電話の取次ぎなど、社内の誰にどんなタイミングでつなぐか、敬語の使い方や確認の仕方も含めて、実際の電話音声とともに動画で示すと、習得しやすくなります。
・席への案内
お客様の人数確認や禁煙・喫煙の確認、歩き方、席案内の声かけなど、自然な対応を動画でみて真似することで、店全体の標準化を図ることができます。
・レストランでの注文受付
お客様への声がけ、復唱のタイミング、料理名の言い方など、流れと気配りをセットで伝えられるため、動画マニュアルで身につけやすいです。
・商品説明
商品の特徴や使い方、他商品との違いを説明するなどの動画は、社内研修や営業支援ツールとしてだけでなく、Webサイトや展示会などでの活用により、お客様向けコンテンツとしても有効です。社内外で幅広く再利用できるので、効率的かつ効果的な情報伝達手段となります。
・エレベーターでの案内
上司やお客様が同乗する場合は、先に乗って操作パネルの前に立ち、行き先階を確認・操作する、降りる際は先にお客様を降ろし、本人は最後に出るなどの細やかな気配りを、シーン別に動画で示すとマナーが身につきます。
・レジ接客
商品の受け取り方や袋詰め時の声がけ、カトラリー類の有無など、繰り返し動画を見ることで動作を伴う業務を直感的に覚えることができます。
・ホテルチェックイン対応
ホテルのチェックイン対応は、接客品質の第一印象を決める重要な業務のため、動画マニュアルにすることで、表情や声のトーン、動作など文字では伝わりにくい接客のコツを視覚的に学べます。
新人スタッフも実際の流れを具体的に把握でき、サービスの均一化にもつながります。
・お子様連れのお客様対応
ベビーカー対応やメニューの説明、プレイルームの案内など、通常のお客様案内よりさらに柔らかく丁寧な対応を促すような動画を見せることで安心感のある接客を店舗全体に浸透させることができます。
解説内容&人の動きを元に自動で手順分割!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」
4.まとめ
今回は"動画マニュアルを作成するべき業務64選"を解説しました。
動画マニュアルは、人の手作業や機器の操作・点検、対人コミュニケーションなど”実際の動きややりとりの流れ”が重要な業務と、ITシステムの使い方や、安全対策など文字や画像だけでは習得しづらく、日常業務より頻度が少ないため”動画で見せる方がわかりやすく効率的”になるような業務に有効です。
また、習熟度の可視化や、標準化をより進めたい場合、動画マニュアルツールを活用すれば「視聴する動画」から「教育・管理できる動画」を運用することもできます。
このような動画マニュアルを限られた時間で効率よく作成したい場合は「Dive」がおすすめです。直感的に動画マニュアルの制作・運用ができる機能をご用意しており、その中でもアップロードしてメールの到着を待つだけで動画編集の9割が完了できるからです。
下記より詳細を確認できます。
ご覧いただきありがとうございました。
アップロードして放置で動画編集9割完了!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」